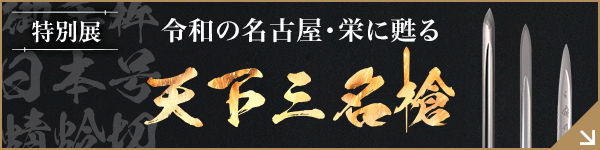名古屋刀剣博物館/名古屋刀剣ワールド(名博メーハク) 名古屋刀剣博物館鑑賞バスツアー 旅のレポート
特別展「天下三名槍」
名古屋刀剣博物館/
名古屋刀剣ワールド(名博メーハク) 名古屋刀剣博物館鑑賞バスツアー
旅のレポート
特別展「天下三名槍」

2025年(令和7年)3月22日(土)・23日(日)に、「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」で開催された特別展「天下三名槍」(てんかさんめいそう)をいち早く鑑賞・満喫できる「名古屋刀剣博物館鑑賞バスツアー」が実施されました。
この特別展「天下三名槍」は、2025年(令和7年)3月22日(土)から6月1日(日)までの期間で開催されており、本バスツアーはその開催初日にあたる3月22日から催行された企画となります。
名古屋刀剣博物館の鑑賞バスツアーは今回で3度目の実施。学芸員による解説を聞きながら館内を巡ることができるほか、今回のバスツアーでは天下三名槍(てんかさんめいそう)の1本である「蜻蛉切」(とんぼきり)を愛槍とした武将「本多忠勝」(ほんだただかつ)ゆかりの地・三重県桑名市を散策しました。「桑名市博物館」や「桑名城跡」、「七里の渡し跡」など、桑名市の旧跡で歴史を感じながら、天下三名槍の魅力を再発見できる「名古屋刀剣博物館鑑賞バスツアー 特別展『天下三名槍』を鑑賞」の2日間をレポートします。
- 目次
現代に甦る「天下三名槍」を堪能するバスツアー
特別展「天下三名槍」とは

名古屋刀剣博物館の北館4階特別展示室では、2025年(令和7年)3月22日(土)~6月1日(日)の期間、特別展「天下三名槍」を開催。本特別展では、「天下三名槍」として知られる3本の槍「御手杵」(おてぎね)、「日本号」(にほんごう)、「蜻蛉切」の写しが一堂に展示されています。
この三名槍の写しはかねてより進行していた「天下三名槍写し制作プロジェクト」により、5年以上の月日をかけて完成した作品です。「写し」とは、元となる刀剣を模して作られた刀剣のこと。名古屋刀剣博物館の三名槍写しは、日本刀工界で最高位とも言える称号「無鑑査」(むかんさ)に認定された「上林恒平」(かんばやしつねひら)刀匠により作刀されました。
旅のスケジュール紹介

フリックによる横スライド仕様となります


名古屋刀剣博物館を鑑賞
特別展「天下三名槍」を誰よりも早く観覧
ツアーの初日は、集合場所である「名古屋駅」(名古屋市中村区)を出発すると、早速特別展「天下三名槍」の会場・名古屋刀剣博物館の北館4階展示室へ。ツアーの参加者は開館より1時間早い9時に博物館へ入館し、だれよりも早く、貸し切りで名古屋刀剣博物館の天下三名槍を堪能することができました。

写しとは言え、天下三名槍が3本揃って展示されることは大変貴重な機会。それぞれ覇気のある堂々とした姿をしており、三名槍を観た参加者は、その迫力に息をのんで見入ってしまいます。また、3本は並んで展示されているので、一目でそれぞれの槍を比較できるところも見どころ。三名槍はいずれも、穂(ほ:槍の刀身)が特に長いものを指す「大身槍」(おおみやり)に分類されていますが、御手杵の穂長が142.3cmであるのに対し、蜻蛉切の穂長は43㎝であることから、大きさの違いがよく分かるのです。
さらに、三名槍の隣には刀身彫刻の名手である「大慶直胤」(たいけいなおたね)、「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)の作品が展示されており、日本号に施された彫刻との違いを見比べて楽しむことができます。
学芸員の説明では天下三名槍の来歴などが紹介されたほか、三名槍写しの制作を手掛けた上林恒平刀匠、日本号の彫りを手掛けた「柳村宗寿」(やなぎむらそうじゅ)氏を紹介。キャプションには書かれていない制作秘話なども聞くことができ、特別展「天下三名槍」への理解を深めて楽しむことができました。

▲学芸員により説明が行われている様子 
▲天下三名槍をじっくり見学
写しを手掛けた現代刀匠と三名槍ゆかりの刀剣

特別展「天下三名槍」では、一番の目玉である三名槍の写しのほか、三名槍写しの制作者・上林恒平刀匠の作品や、人間国宝に認定された「宮入昭平」(宮入行平:みやいりあきひら/ゆきひら)刀匠をはじめとした現代刀匠の作品も鑑賞することができます。現代刀は有名な武将の逸話もないことから、刀剣初心者には近寄りがたい印象があるかもしれません。しかし、今回の紹介では「新しいものは地刃が健全であるため、刃文、地鉄が最も見やすく、初心者にこそ見てほしい」と語られました。
その他、蜻蛉切ゆかりの本多家、御手杵ゆかりの結城家、日本号ゆかりの黒田家に関連する刀剣、本多忠勝の甲冑のレプリカなどが展示されています。なかでも注目したい展示が、御手杵を作刀したと伝わる刀工「義助」(よしすけ)の作と言われる「短刀 銘 義助」(たんとう めい よしすけ)です。御手杵写しは槍であるため見え方は異なりますが、いずれも沸の付いた美しい刃文をしていることが分かるので、刃文や姿などの違いを見比べてみると面白いでしょう。
名古屋刀剣博物館を満喫

特別展「天下三名槍」の展示を鑑賞したあとは、北館2階の展示コーナーへ移動。北館2階は「日本刀とはどのようなものなのか」を紹介する、博物館の導入部分とも言えるコーナーです。日本刀の制作工程や、時代ごとの日本刀の姿を観ることができます。ここでは、学芸員により博物館の説明やキャプションの見方など、名古屋刀剣博物館を最大限楽しむための説明が行われました。
説明のあとは、自由行動。学芸員もフロアを回って1ヵ所ずつ解説をしてくれるので、学芸員による博物館のツアーを楽しみたい方と、自分のペースでじっくり観て回りたい方とに分かれて見学できました。名古屋刀剣博物館では最大200振の日本刀展示に加え、甲冑(鎧兜)、鉄砲、浮世絵、屏風、書画など、鑑賞できる美術品は多岐にわたります。

なかでも鉄砲は約350挺もの数の展示があり、日本に火縄銃が伝来した頃の作品から明治時代までの国内外の鉄砲を一度に観ることが可能。
また、鉄砲には象嵌(ぞうがん:表面に彫った溝に金や銀、石などの異素材をはめ込む技法) や彫刻など、美しい装飾が施されているものがあるのも魅力のひとつです。日本刀と同様に、武器としての実用品としての側面だけでなく、美術品としての価値があることを再発見する人も少なくありませんでした。
貴重な刀剣を手に取って鑑賞

博物館をじっくり鑑賞したあとは、6階にある学習室で刀の鑑賞会が行われました。ここでは、本物の刀剣を実際に手に取って鑑賞することができます。通常、博物館の刀剣を直接手に取って鑑賞する機会はほとんどないため、本ツアーの参加者も手に取って鑑賞するのは初めての方ばかり。刀の鑑賞会はどのように臨めばいいのか、はじめに手を洗う、時計をはじめ、アクセサリー類は外しておくなどの注意事項も丁寧にレクチャーがありました。また、実物を触る前に模造刀を使って刀剣鑑賞の作法を練習することができたため、はじめて刀に触る方でも安心して刀の鑑賞に臨むことができました。
今回鑑賞したのは以下の5振の刀剣です。いずれも著名刀工の手による作品で、なかには重要美術品の名刀も含まれており、ほかでは味わえない貴重な体験となりました。
| 名称 | 時代 | 鑑定区分 |
|---|---|---|
| 刀 折返銘 備前国住雲重 |
南北朝 時代 |
重要 美術品 |
| 小太刀 銘 長光 |
鎌倉 時代 |
重要 美術品 |
| 短刀 銘 洛陽住藤原国広 慶長十五仲夏日 |
江戸 時代 |
重要 刀剣 |
| 太刀 朱銘 友成 |
平安 時代 |
重要 刀剣 |
| 脇差 銘 勢州桑名住村正 |
室町 時代 |
特別 保存刀剣 |
刀の鑑賞会では、ガラス面の反射もないことから地鉄や刃文をより詳細に観察することができます。手に持った刀剣は角度を変えることで光が反射し、刃文がはっきりと浮かび上がる様子を観察でき、ガラス越しでは見えない映りや沸(にえ)・匂(におい)などの繊細な働きを目に焼き付け、堪能できたひと時となりました。

ミュージアムショップで旅のお土産を吟味する
名古屋刀剣博物館の北館1階にはミュージアムショップがあります。ミュージアムショップでは所蔵刀剣のポスターや図録、模造刀、浮世絵のレプリカ、Tシャツをはじめとしたオリジナルグッズが数多く販売されていました。
なかでも目を引いたのは、天下三名槍展に際して作られたオリジナルグッズや本多忠勝の関連グッズです。おすすめなのが、三名槍写しのアクリルスタンド。縦置き、横置きの2種類があり、インテリアや好みに合わせて選べます。刀身彫刻や姿が忠実に再現されており、三名槍展を観た旅の思い出にぴったりのグッズです。三名槍展で展示中の本多忠勝の甲冑アクリルスタンドや、本多忠勝の浮世絵缶バッジなどもありました。
刀剣ワールド名古屋・丸の内 別館で現代刀を知る!

続いて訪れたのは、名古屋市中区の東建コーポレーション本社に併設された「刀剣ワールド名古屋・丸の内 別館」。「名古屋城」や街並み保存地区「四間道」(しけみち)の徒歩圏内で、名古屋の歴史を感じられる立地にある刀剣ワールド名古屋・丸の内 別館には、刀剣、甲冑、浮世絵のほかに、屏風や櫓時計(やぐらどけい)などの調度品を展示しています。通常は平日のみの開館ですが、土、日曜日に開催されたバスツアーでは参加者のため、特別に見学をすることができました。

刀剣ワールド名古屋・丸の内 別館では、2025年(令和7年)2月26日(水)~6月27日(金)までの間、通常展示に加えて企画展「無鑑査刀匠の刀」を開催中です。1階の企画展示室には、天下三名槍写しを制作した上林恒平刀匠と同じ肩書を持つ無鑑査刀匠の刀剣を展示。「無鑑査」とは、日本美術刀剣保存協会(日刀保)が主催するコンクールにおいて特賞を複数回以上受賞したことのある、きわめて優れた刀匠に贈られる肩書です。
ここでは、備前刀復興の祖と言われる「藤原俊光/今泉俊光」(ふじわらとしみつ/いまいずみとしみつ)刀匠の作品「刀 銘 天命寿楽 藤原俊光」や、日刀保のコンクール「現代刀匠展」における最高峰の賞「正宗賞」を獲得した「宮入法廣」(みやいりのりひろ)刀匠の作品「刀 銘 宮入法廣作之/平成十一年弥生」などが鑑賞できました。
2階の展示ブースでは、刀剣、浮世絵、屏風、櫓時計などが展示されているほか、解説動画や、時代による日本刀の変遷について解説したパネルなどもあり、学芸員へ作品についての質問をしながら日本刀の理解を深めることができます。
刀剣ワールド桑名・多度 別館で室町時代の刀と槍を知る!
ホテル多度温泉で一泊

日帰りツアーの参加者は名古屋駅で解散し、宿泊ツアーの参加者を乗せた観光バスは三重県桑名市多度町にある「ホテル多度温泉」へ。ゴルフ場「東建多度カントリークラブ・名古屋」に隣接しており、「クラブハウス本館」、「レジデンス新館」、「火水風別館」3棟の宿泊施設があるホテルです。ホテル内には「刀剣ワールド 桑名・多度 別館」があり、レジデンス新館3階の「ローズウッド」、「ペガサス」、クラブハウス本館の「コンペルーム」にて刀剣、甲冑等が展示されています。
「レストラン鳳凰」で夕食を取ったあとは、「空中CGアニメ・ナイトレーザーショー」を鑑賞。ゴルフ場の夜空を舞台に、日本刀や歴史をモチーフにしたアニメーションや、鮮やかなレーザーショーが繰り広げられました。

三名槍が制作された時代の刀と槍を観る

2日目は、刀剣ワールド桑名・多度 別館の見学からスタート。レジデンス新館のローズウッドでは、2025年(令和7年)3月4日(火)~7月6日(日)まで、企画展「室町時代の刀と槍」を開催中です。
室町時代の日本刀は、前期と後期で異なるのが特徴です。これは室町時代前期に大きな戦が起こらなかったことと、戦法の変化がかかわっていると考えられています。また、室町時代は「打刀」(うちがたな)と呼ばれる寸法が短い日本刀が登場した、刀剣史におけるひとつの転換点とも言える時代なのです。
さらに、室町時代は「薙刀」(なぎなた)や「大太刀」(おおだち)に代わって槍が戦場で活躍し始めた時代。天下三名槍が制作されたのも室町時代であるため、名古屋刀剣博物館に展示されている天下三名槍写しと、「室町時代の刀と槍」に展示されている槍を見比べて、違いや共通点を探すことができます。
天下三名槍が作られた時代の日本刀と槍を鑑賞して、刀剣史を知ることができる体験ができました。
武将に愛された孫六兼元と和泉守兼定
刀剣ワールド桑名・多度 別館で鑑賞できるのは「室町時代の刀と槍」だけではありません。ペガサスには桑名市ゆかりの刀工「村正」(むらまさ)の作品が展示されたコーナーがあり、村正の特徴的な茎(なかご)の形や、鋭い刃文をじっくり鑑賞することができます。
コンペルームには甲冑や火縄銃、陣笠、鐙(あぶみ)などの武具、馬具が展示されているだけでなく、岐阜県関市を代表する刀匠「孫六兼元」(まごろくかねもと)と「和泉守兼定」(いずみのかみかねさだ)の作品をピックアップした「兼元・兼定コーナー」が見どころ。
孫六兼元は「三本杉」と呼ばれる、尖り互の目(ぐのめ)が3つ並んだ独特な刃文が特徴で、「兼元・兼定コーナー」の作品にも観ることができます。和泉守兼定は、室町時代後期に関市で活動し、戦国武将の刀剣をいくつも作刀したことで知られる名匠・2代目兼定と、江戸時代末期に会津藩(現在の福島県西部)で活動し、「土方歳三」(ひじかたとしぞう)の愛刀を作刀した11代目兼定が有名です。「兼元・兼定コーナー」では2代目、11代目両名の作品を鑑賞することができました。
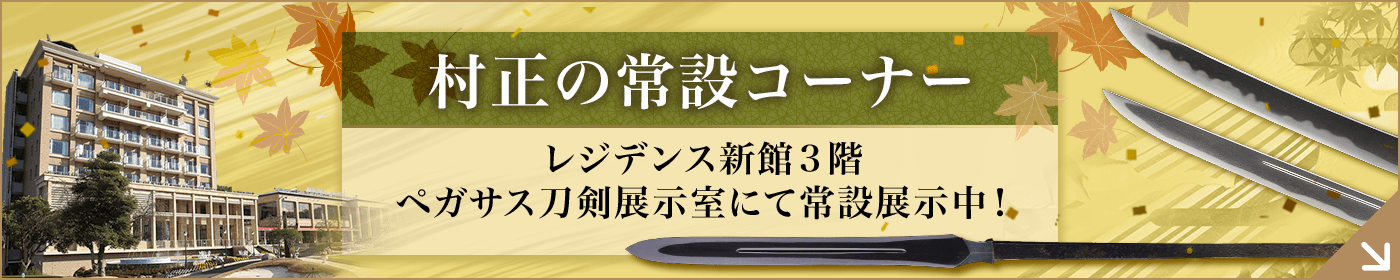
桑名市の史跡を満喫
桑名市博物館で桑名市ゆかりの刀剣を知る

刀剣ワールド桑名・多度の鑑賞後は、「桑名市博物館」へ。桑名市博物館は、江戸時代に栄えた桑名藩に関する資料や、桑名市が創始とされる伝統工芸「萬古焼」(ばんこやき)など、桑名市の歴史、民俗を中心に所蔵、展示を行っている市立博物館です。ツアーの当日は、春の企画展「茶道具✿春らんまん」と「刀剣セレクションⅢ―桑名ゆかりの刀剣―」という展示が行われており、「茶道具✿春らんまん」では花の茶道具、春の日本画など、春らしい館蔵品コレクションが披露されていました。「刀剣セレクションⅢ―桑名ゆかりの刀剣―」では、桑名市ゆかりの刀工・村正の刀や、蜻蛉切の作者「藤原正真」(ふじわらまさざね)の短刀など、桑名市ならではの刀剣を鑑賞。桑名市の魅力をたっぷりと感じました。
桑名市の史跡を散策し、桑名藩の祖・本多忠勝に思いをはせる

桑名市の名物グルメ・はまぐり料理のお店「魚重楼」(うおじゅうろう)にて昼食後は、東海道の宿場町として栄えた桑名市の旧跡を散策。桑名藩初代藩主・本多忠勝の墓所がある「袖野山 浄土寺」(しゅうやさん じょうどじ)や、東海道宿場町の要所「宮宿」(名古屋市熱田区)から「桑名宿」までをつないだ海路の渡船場「七里の渡し跡」や「桑名城跡」、「桑名宗社」を巡りました。
七里の渡しのそばにある桑名城は、自然の川を利用して築かれた水城(みずじろ)です。城下町は桑名城を中心に川沿いに整備され、街のあちこちには運河を張り巡らせることで、物資や人を運ぶネットワークを築いていました。城下町はこの水路によって活性化し、東海道唯一の海路を持つ宿場町として栄えていたという歴史があります。

桑名市散策の道中は、桑名市名物のはまぐりや七里の渡しが描かれたかわいらしいマンホールに足を止めるなど、和気あいあいとした雰囲気の中で、終始穏やかに楽しみました。桑名城跡では本多忠勝像の前で写真撮影を行い、桑名市の歴史をたどりながら、特別展「天下三名槍」を心行くまで満喫できる旅を締めくくりました。
バスツアーで巡った桑名市の散策マップ
名槍を巡る、知と感動の2日間を終えて
名古屋刀剣博物館での特別展「天下三名槍」と、三重県桑名市の史跡を巡る今回のバスツアーは、刀剣や歴史の魅力をじっくりと味わっていただける機会となりました。
館内では、写しでありながらも圧倒的な存在感を放つ槍の展示を通して、実物さながらの迫力を体感されたことと思います。学芸員による丁寧な解説に耳を傾ける中で、槍の背景や、それを手にした武将たちとのつながりにも理解が深まったのではないでしょうか。
また、忠勝公ゆかりの地・桑名市を実際に歩くことで、歴史をより身近に感じられたのではないかと思います。刀剣そのものに加え、土地の空気や景色に触れることで、当時の時代に想いを馳せるひとときとなっていれば嬉しく思います。
刀剣ファンの方はもちろん、歴史好きの方にとっても楽しめる内容で、ご参加の皆さまには知的な刺激とともに、心豊かな時間をお過ごしいただけたのではないかと感じております。
次回は、特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」について、さらに奥深い刀剣の世界の旅のレポートをご案内します。どうぞご期待ください。